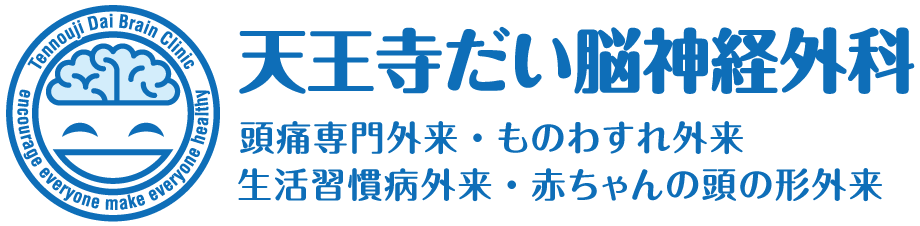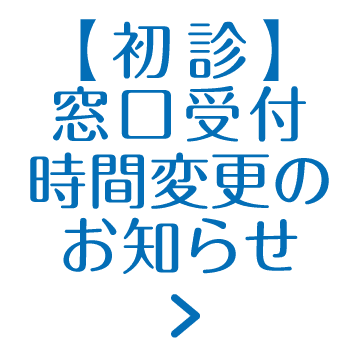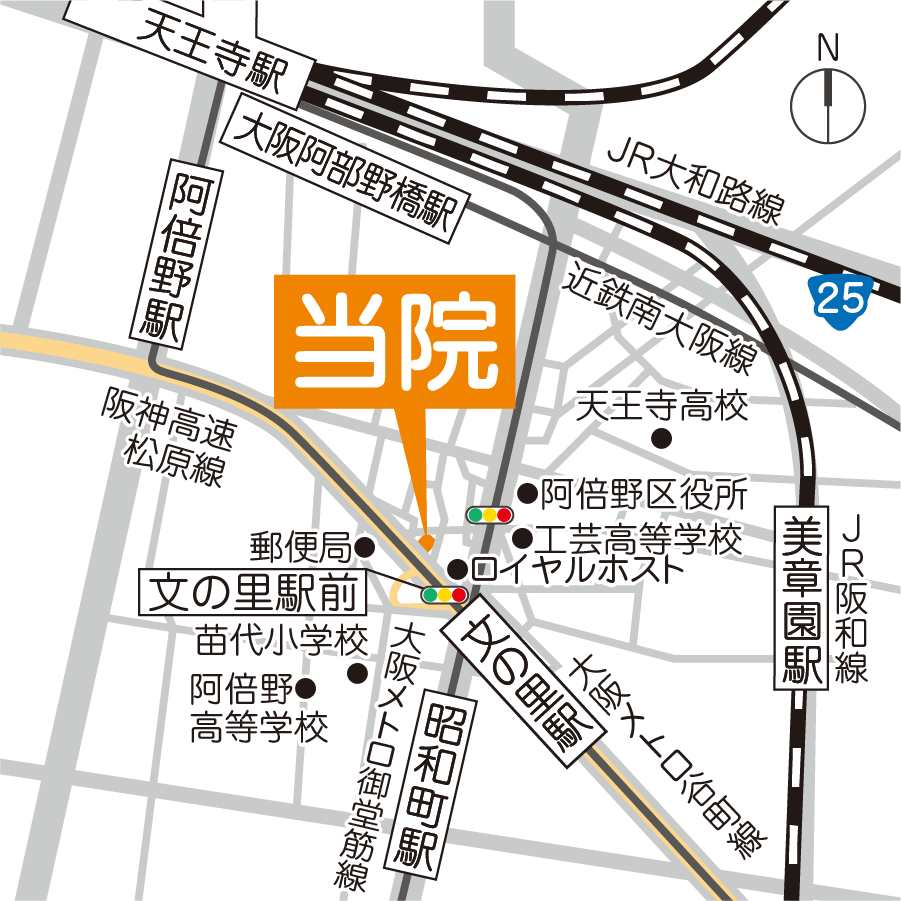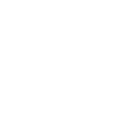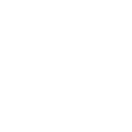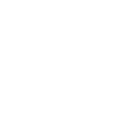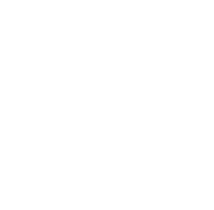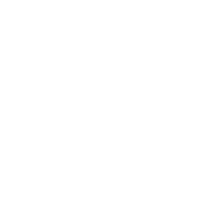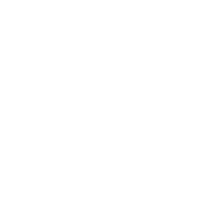パーキンソン病について
パーキンソン病は、脳の中の「黒質(こくしつ)」という部分にある神経細胞が少なくなることで起こる病気です。
この神経細胞は「ドパミン」という体の動きを調節する物質を作っています。
- 約15万人日本全国の患者数
- 50-65歳発症が多い年齢層
- 1,000人中1~2人発症率
適切な治療により、一般の方とほとんど変わらない寿命を保つことができます。
パーキンソン病はゆっくりと進行する病気であり、新しい治療法も次々と登場しています。決して諦める必要はありません。
| 患者数 | 日本全国で約15万人 (1,000人に1〜2人の割合) |
|---|---|
| 発症年齢 | 50〜65歳に多い (高齢になるほど多くなる) |
| 男女比 | やや男性に多い |
| 進 行 | ゆっくりと進行する病気 |
| 寿 命 | 適切な治療により、一般の方とほとんど変わらない |
パーキンソン病について解説動画もご覧ください
パーキンソン病の主な症状
主な運動症状(4大症状)
-
安静時の振戦(しんせん・ふるえ)
- 具体的な現れ方
-
- 安静時の手足の震え
- 1秒間に4〜6回のリズム
- 動かすと震えが止まる
- 日常生活での影響
-
- 字を書くのが困難
- 食事で手が震える
- 人前で気になる
-
筋強剛(きんきょうごう・こわばり)
- 具体的な現れ方
-
- 筋肉が硬くなる
- 関節が動かしにくい
- 歯車のような抵抗感
- 日常生活での影響
-
- 肩こりがひどくなる
- 腕が振れない
- 表情が乏しくなる
-
無動・寡動(むどう・かどう)
- 具体的な現れ方
-
- 動作が遅くなる
- 小さな動作が困難
- 同時に2つの動作ができない
- 日常生活での影響
-
- ボタンをかけるのが困難
- 歩き始めが困難
- 字が小さくなる
-
姿勢反射障害
- 具体的な現れ方
-
- バランスを崩しやすい
- 転倒しやすくなる
- 前かがみの姿勢
- 日常生活での影響
-
- 歩行時の転倒リスク
- 方向転換が困難
- 階段の昇降が危険
その他の症状(非運動症状)
-
自律神経の症状
-
- 便秘(最も多い症状の一つ)
- 頻尿・夜間頻尿
- 立ちくらみ(起立性低血圧)
- 汗をかきやすい、または汗をかかない
-
-
精神・認知の症状
-
- うつ気分・意欲の低下
- 不安感
- 認知機能の変化
- 幻視(実際にないものが見える)
-
-
その他の症状
-
- 嗅覚の低下
- 睡眠障害
- 痛みやしびれ
- 疲れやすさ
-
早期発見のためのチェックリスト
以下の症状がある場合は、早めに医師にご相談ください
- 手や足が安静時に震える
- 歩行時に片方の腕が振れない
- 歩き始めの第一歩が出にくい
- 字が以前より小さくなった
- ボタンをかけるのが難しくなった
- 表情が乏しくなったと言われる
- 声が小さくなった
- 嗅覚が低下した
- 便秘がひどくなった
- 夜間頻尿が増えた
診断方法と検査
パーキンソン病の診断は主に症状の観察によって行われます。
確定診断ができる単一の検査はありませんが、以下の方法で総合的に判断します。
神経学的診察
-
目的
症状の確認
-
内容
歩行、筋肉の状態、反射などを詳しく調べます
MRI検査
-
目的
他の病気の除外
-
内容
脳梗塞や脳腫瘍など他の原因がないかを確認
DaTscan(ダットスキャン)
-
目的
ドパミン神経の評価
-
内容
ドパミン神経の減少を画像で確認する特殊検査
MIBG心筋シンチ
-
目的
自律神経の評価
-
内容
心臓の自律神経の状態を調べる検査
治療方法
薬物療法
パーキンソン病の治療の基本は薬物療法です。不足したドパミンを補ったり、ドパミンの働きを助けたりする薬を使います。
L-ドパ(レボドパ)
-
働き
ドパミンの補充
-
特徴
最も効果的な薬/高齢者の第一選択/長期使用で効果の変動あり
ドパミンアゴニスト
-
働き
ドパミン受容体の刺激
-
特徴
効果が長持ち/若い方の第一選択/幻覚に注意が必要
MAO-B阻害薬
-
働き
ドパミンの分解抑制
-
特徴
L-ドパの効果を延長/安静時振戦のみの方には第一選択/意欲向上効果、痛みにも効く場合も
COMT阻害薬
-
働き
L-ドパの分解抑制
-
特徴
ウェアリングオフを改善/L-ドパと併用、合剤もある/効果時間を延長
リハビリテーション
薬物治療と併せて、リハビリテーションも重要な治療法です。特に一歩目が踏み出せないすくみ症状には薬物療法の効果がいまいちのことも多くリハビリが重要です。
-
理学療法
歩行訓練、バランス訓練
-
作業療法
日常生活動作の訓練
-
言語療法
発声、嚥下訓練
進行期パーキンソン病の治療選択肢
より良い毎日を送るための新しい選択肢
パーキンソン病は進行性の疾患ですが、適切な治療により症状をコントロールしながら生活の質を保つことができます。従来のお薬による治療だけでは十分な効果が得られなくなった場合でも、新しい治療法により、患者様の90%以上が生活の質の向上を実感されています。
進行期治療の3つの選択肢
進行期に現れる主な症状
症状チェックリスト
- お薬の効果が以前より短時間になった(2~3時間で切れる、オフ症状)
- お薬が効いている時間と効いていない時間の差が大きくなった
- 体が勝手に動いてしまうことがある(ジスキネジア)
- 足がすくんで歩けなくなることが増えた
- 姿勢を保つのが難しくなった
- 日常生活の予定が立てにくくなった
これらの症状が現れても、新しい治療選択肢により改善が期待できます。決して諦める必要はありません。
進行期パーキンソン病の目安「5-2-1ルール」
進行期の目安として「5-2-1ルール」というものが存在します。
- 5:レボドパ製剤の内服が1日5回以上
- 2:オフ症状が1日に2時間以上
- 1:日常生活に支障のあるジスキネジアが1日に1時間以上
ウェアリングオフ現象について
ウェアリングオフとは、お薬(主にレボドパ)の効果が徐々に短時間になり、次の服薬前に症状が戻ってしまう現象です。「薬が切れる」と表現されることもあります。
| 時間帯 | 従来の状態 | ウェアリングオフが起こる状態 |
|---|---|---|
| 服薬直後 | 症状改善 | 症状改善 |
| 2~3時間後 | 効果持続 | 症状が戻り始める | 次の服薬前 | 効果持続 | 症状が強く現れる |
LCIG療法(デュオドーパ)について
LCIG(levodopa-carbidopa intestinal gel治療)療法は、レボドパ・カルビドパ配合経腸用液(商品名:デュオドーパ)を用いた治療法です。ゲル状のお薬を小腸に直接、持続的に投与することで、安定した効果を得ることができます。
LCIG療法の主な特徴
-
24時間安定した効果
お薬を持続的に投与するため、効果の波が少なくなります
-
ウェアリングオフの改善
「薬が切れる」時間を大幅に減らせます
-
ジスキネジアの軽減
不随意運動を抑えることができます
-
生活の質向上
予測可能な症状コントロールにより、外出や活動がしやすくなります
- 治療効果実績
-
- ウェアリングオフ時間:平均6時間→2時間に短縮
- オン時間:1日約4時間延長
- ジスキネジア:約50~70%の患者様で改善
- 生活の質:90%以上の患者様で向上
ウィアレブ(持続皮下注療法)について
ウィアレブは、2023年に承認された新しい治療選択肢です。ホスレボドパ・ホスカルビドパという成分を、携帯型の小さなポンプで24時間皮下に注射し続ける治療法です。
ウィアレブの主な特徴
-
手術不要
皮下注射のため、お腹を切る手術が必要ありません
-
携帯可能
小型のポンプで日常生活に支障がありません
-
24時間効果
持続的な投与により安定した症状コントロールが可能
-
導入が容易
外来でも開始できる場合があります
- 治療効果実績
-
- ウェアリングオフ時間:1日平均2.7時間の短縮
- オン時間:薬が効いている時間が約3時間延長
- 日常生活の改善:85%の患者様で生活の質が向上
- 症状の安定性:24時間持続効果により予定が立てやすい
DBS手術(脳深部刺激療法)について
DBS(Deep Brain Stimulation:脳深部刺激療法)は、脳の深部に細い電極を挿入し、電気刺激によってパーキンソン病の症状を改善する治療法です。日本では2000年から保険適用となり、多くの患者様が良い結果を得ています。
DBSシステムの構成要素
-
電極(リード)
脳の深部に植え込む極細の電極(直径約1.3mm)
-
延長ケーブル
電極と刺激装置をつなぐ体内ケーブル
-
刺激装置(IPG)
胸部に植え込む電池式の刺激装置
-
プログラマー
刺激条件を調整する外部機器
- 改善が期待できる症状
-
- 振戦(ふるえ):80-90%の患者様で顕著な改善
- 筋固縮(筋肉のこわばり):70-80%の患者様で軽減
- ウェアリングオフ:オフ時間を50-80%短縮
- ジスキネジア:薬物減量により軽減
- 歩行機能:歩幅や歩行速度の改善
治療選択の考え方
どの治療法が最適かは、患者様の症状、年齢、生活スタイル、ご家族のサポート状況などを総合的に考慮して決定します。
| 考慮要素 | LCIG療法 | ウィアレブ | DBS手術 |
|---|---|---|---|
| 開始の簡単さ | ○ (小手術必要) |
◎ (手術不要) |
△ (脳手術必要) |
| 効果の持続性 | ◎ (24時間安定) |
◎ (24時間安定) |
◎ (長期持続) |
| 振戦への効果 | ○ | ○ | ◎ |
| 日常生活への影響 | ◎△ (ポンプ携帯) |
○ (軽量ポンプ) |
◎ (体内完結) |
| 合併症リスク | ○ (感染等) |
○ (皮膚トラブル) |
△ (手術リスク) |
| 年齢制限 | なし | なし | 75歳以下推奨 |
| 導入期間 | 2-4週間 | 1-2週間 | 1-2ヶ月 |
治療選択の指針
-
症状の特徴
振戦が主体→DBS、オフ時間が長い→LCIG/ウィアレブ
-
年齢
75歳以上→LCIG/ウィアレブを検討
-
手術への意向
手術を避けたい→ウィアレブを検討
-
生活スタイル
アクティブ→DBS、在宅中心→LCIG/ウィアレブ
-
認知機能
軽度低下がある場合→LCIG/ウィアレブ
日常生活での注意点とアドバイス
運動と活動
- 毎日の運動:散歩、ストレッチを1日30分以上
- 歩行目標:1日8000歩を目安に
- 姿勢の意識:鏡を見て正しい姿勢を確認
- 転倒予防:手すりの設置、段差の解消
食事と栄養
- バランスの良い食事を心がける
- 便秘予防:食物繊維と水分を十分に
- L-ドパ服用時:タンパク質摂取のタイミングに注意
- 骨粗鬆症予防:カルシウム、ビタミンDの摂取
睡眠と休息
- 規則的な睡眠習慣を保つ
- 日中の適度な活動で夜の睡眠を改善
- 就寝前のリラックスタイムを設ける
- 睡眠障害は医師に相談
ご家族へのアドバイス
- 患者様の自立を尊重する
- できることは見守り、必要な時にサポート
- 感情の変化に理解を示す
- ご家族自身のケアも大切に
よくあるご質問
明るい未来への一歩
パーキンソン病の治療は日々進歩しています。現在ご紹介した治療法により、多くの患者様が症状の大幅な改善を実感され、積極的な社会参加を続けておられます。
これらの治療により、患者様が生活の質の向上を実感されています。お孫さんとの時間を楽しまれたり、趣味を再開されたり、旅行に出かけられたりと、新しい可能性が広がっています。
患者様・ご家族へのメッセージ
- 諦めないでください 新しい治療選択肢があります
- 一人で悩まないでください 専門医療チームがサポートします
- 希望を持ってください 多くの方が症状の改善を実感されています
- 積極的に相談してください 早期の治療検討が重要です
- 生活を楽しんでください 治療により新しい可能性が広がります
「大切なのは、一人で悩まず医療チームと相談すること、ご自身に最適な治療選択肢があることを知ること、そして希望を持ち続けることです。」
参考文献・関連リンク
診療ガイドライン・学術文献
- 日本神経学会:パーキンソン病診療ガイドライン2018
- 厚生労働省:指定難病パーキンソン病(指定難病6). 難病情報センター
- 神経変性疾患領域における基盤的調査研究班:パーキンソン病の療養の手引き
- 慶應義塾大学病院パーキンソン病センター:パーキンソン病について
主要な学術論文
- Antonini A, et al. Levodopa-carbidopa intestinal gel in advanced Parkinson’s disease: Final results of the GLORIA registry. Parkinsonism Relat Disord. 2019; 68: 68-74
- Poewe W, et al. Efficacy and safety of foslevodopa/foscarbidopa in Parkinson’s disease: A randomized clinical trial. Mov Disord. 2022; 37: 1892-1903
- Okun MS. Deep-brain stimulation for Parkinson’s disease. N Engl J Med. 2012; 367: 1529-1538
- Deuschl G, et al. A randomized trial of deep-brain stimulation for Parkinson’s disease. N Engl J Med. 2006; 355: 896-908
- Postuma RB, Berg D, Stern M, et al. MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson’s disease. Mov Disord. 2015;30(12):1591-601
関連する学会・団体
- 日本神経学会 – パーキンソン病診療ガイドラインの策定・改訂
- 日本パーキンソン病・運動障害疾患学会 – 専門的な研究・診療の推進
- 全国パーキンソン病友の会 – 患者・家族のサポート活動
- 神経変性疾患領域における難病の医療水準の向上や患者のQOL向上に資する研究班
免責事項
- 本資料は患者様とご家族への情報提供を目的としており、医学的助言の代替となるものではありません
- 治療方針の決定については、必ず主治医にご相談ください
- 薬剤情報や治療効果については、個人差があります
- 最新の治療情報については、主治医または医療機関にお問い合わせください